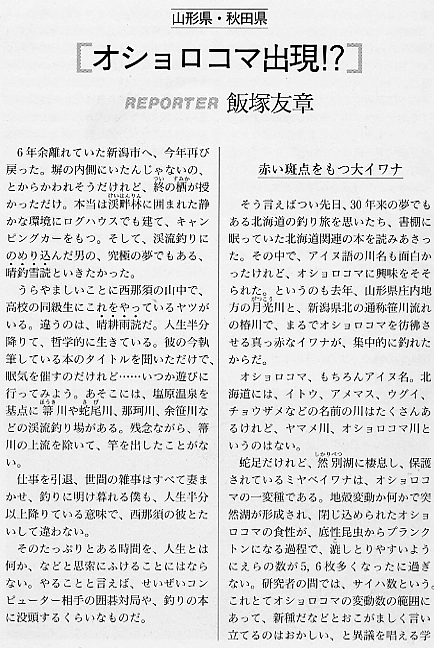
クニマス再生プロジェクト(田沢湖よ甦れ)
まづは1997年発行のある渓流釣りの本のコラムをみていただきたい。
「みちのく再発見」というサブタイトルがついていたように思う。
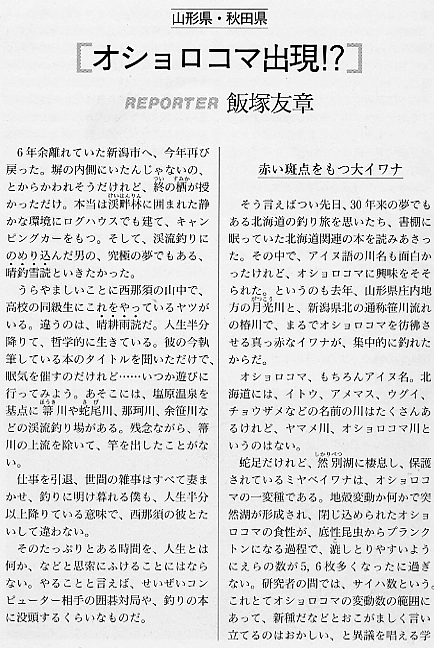
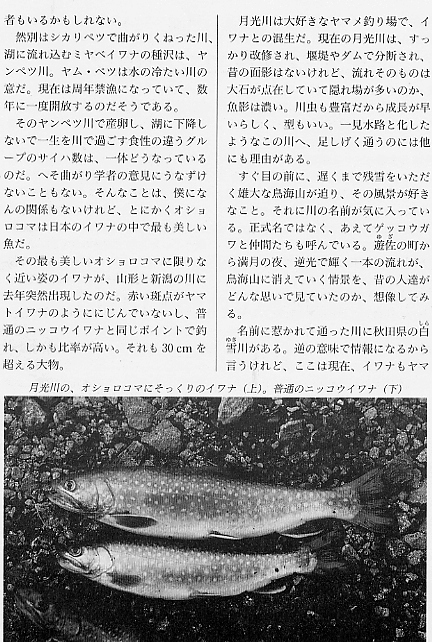
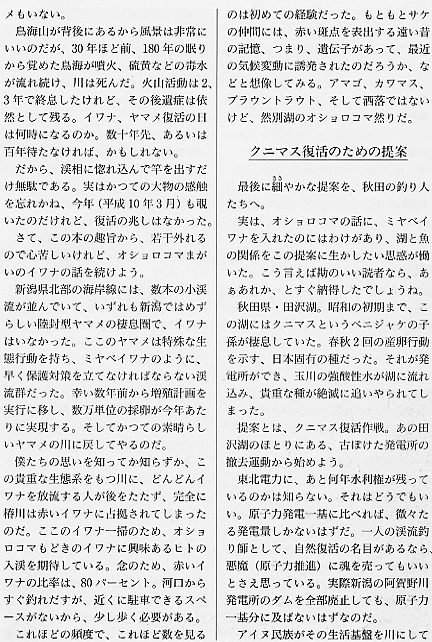
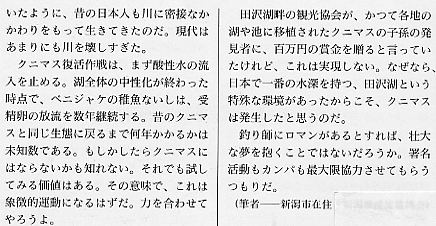
クニマス(Oncorhynchus nerka kawamurai:JORDAN et
McGREGOR)
という訳で、クニマス復活にかける夢実現のために、
会の予算を貰ってまづは行動を起こす事にした。
現在の田沢湖の実情はどうなのか、サケ科の魚にとって致命的なファクターはPhだ。
玉川上流のダムで中和措置がされていても、田沢湖のPhは測定全地点で5.8前後だった。
サケはPh6以下になると、つまり酸性になると産卵行動を止めるといわれている。


水質計測 田子像下での測定値5.80だった
水質の調査は、Ph,DO,溶存酸素など数項目を3〜4地点で朝夕2日間実施した。
Phについていえばほとんど変化はなかった。やはりというか当然その数値は、
想像していた範囲内だった。これではイワナやニジマスをいくら放流しつづけても
棲息できるはずがない。流れ込む谷川の水の回りでうろうろするだけだ。
新潟を出発するとき、この運動をどんな容で展開したらいいのか、
正直なところ、明確な方針があったわけではない。クニマスを見つけたら、
500万円の賞金をだすと言っている、観光協会あたりが話を聞いてくれるかもしれない。
そこでぼくたちの計画を開陳して、運動の取っ掛かりが出来れば、最初の
田沢湖訪問はまあ成功と考えていた。
ところが、インターネットで見つけた宿が、偶然とは言え
ある出会いを用意していてくれたのである。
その宿は朝から夜までジャズが流れていた。知っている曲もあれば、
まるで知らない音楽もあった。妙に懐かしい雰囲気だった。
その日宿泊客はぼくたち3人以外にいなかった。いい年こいたおじさん(いや老人)
が、コーヒーを飲んだり、本を読んだりしていると、当然のように宿のマスターが質問してくる。
『ご旅行ですか?』
『ええ、まあ。ところで食事が終わったら、田沢湖のことについてお聞きしたいのですが・・・』
ペンション・サウンズグッドの夕食は、オリジナル料理でどれも美味しかった。
食事が終わってから、カウンター越しにマスターに、田沢湖へやって来た目的を話した。
クニマスの復活活動をやりたいのだと、途方もない夢を延々と語りつづけた。
『それでしたら、明朝いい人を紹介しましょう。場所を教えますから、尋ねてみてください』
前日小雨に煙っていた田沢湖は、翌朝すっかり晴れ上がっていた。
部屋の窓から、まだ芽吹き始めたばかりの雑木林を通して見えた。
湖面がキラッと輝いていているのが絵になっていた。
まだ寝息を立てている相棒を起こさないよう、カメラを下げて宿を出た。
湖岸まで2分とかからない。湖一周道路にライトバンが止まっていた。
水際を何か探しながら歩いている人を見かけた。

赤いアノラックの人に近づいた。何事にもまだ好奇心は残っている。
「失礼ですが、何を捜しているのですか?」
『化石ですよ』
化石の収集とは言え、田沢湖に深く関わっている大学の研究者、とそのとき思った。
「大学のかたですか?」とぼく。
『いやアー、地元の愛好者ですよ』
その日(2003年4月22日)田沢湖の水位は平水の2.5M下がっていて、
そのために何万年前かのブナの葉っぱなどの化石が見つかるのだという。
1940年以降、玉川の強酸性水が、発電所の導水管から田沢湖に流れ込んだ。
それまで湖水面の変動は10Cmに満たないものだったそうだ。
田沢湖はそのとき以来、酸性化し、水位の変動が激変したのである。
酸性もさることながら、湖岸の砂利に産卵していたクニマスの卵は、
干からびて、2度と子孫を残す機会を失ってしまった。
クニマスの絶滅はあっという間のできごとだったのである。
地元の研究者と、立ち話に費やした時間はそんなに長くはなかった。
『実は、あなたと同じような運動をしている仲間で、事務局長をしているのが近所にいます。』
「是非紹介してください。サウンズグッドには8時半までいます。
会いたいとつたえてくださいますか?」
彼は化石探しを中断して、急いで車へ戻っていった。
朝食の途中で、電話のベルが鳴った。宿を出るとき、
マスターは手書きの地図を用意していてくれた。
想像した通り、会う人は同じだったのである。
田沢湖の外輪丘を降りて、玉川の橋を渡ると、彼の家はすぐわかった。
=田沢湖に命を育む会=事務局長 杉山ハヤト 名刺の肩書きである。
長時間に渡り彼らの運動の推移を聞き、ともすれば挫折しそうにも思える活動を、
シンポジュームなどを開いて、全国的な問題としてゆきましょう。
ぼくたちも全面的にバックアップします。そんな話でお別れした。
彼らの運動の一部として、ぼくたちの目指すロマン、クニマス復活作戦は、
完全に融合したものになると確信した。
陶器工場の一角で、ぼくたちの話を聞いてくれた、
彼の奥さんの、輝くような目が印象的だった。
田沢湖をこのまま永久に死の湖にして置いてよいものか。
地元の熱い思いが十分に伝わってきたのである。
田沢湖に命を育む会 事務局
Tel: 0187−43−1540
E-mail: hayasugi@f2.dion.ne.jp
どうかみなさん、励ましのメールでも、カンパでも協力をお願い致します。